-
speaker 01
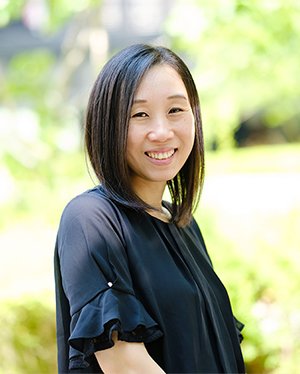
M.Y.
ベル・データ株式会社
Power事業部 Power統括部 第1インフラストラクチャー・サービス
システムエンジニア -
speaker 02

W.T.
milab株式会社
システムエンジニア -
speaker 03

E.M.
ベル・ホールディングス株式会社
人事部 -
speaker 04

A.Y.
ベル・データ株式会社
ビジネス推進本部 業務推進部 -
speaker 05

M.M.
ベル・データ株式会社
Power事業部 Power統括部 テックセールス
営業

未来を切り拓くBELLの女性リーダーたち
BELLグループ各社で活躍する5名の女性管理職が集まり、
キャリア形成の道のりや管理職としての
やりがい・葛藤、ワークライフバランスについて語り合いました。
それぞれの立場から見えるBELLグループの魅力、そして一人ひとりが思い描くキャリアとは——。
新卒入社、転職、産休・育休取得――多様なキャリアストーリー
-
私が入社した2000年当時と比較すると、女性社員はもちろん女性管理職も徐々に増え、心強く感じています。性別を前提として仕事やキャリアを語るべきではないものの、多様性の観点からも皆さんには個性を活かしたリーダーシップを発揮し、後進のロールモデルとなって欲しいというのが私の思いです。この機会に、互いに経験や知見を共有できると嬉しいです。
-
まさに、ここ数年は社会的な働き方改革の推進に伴い、女性社員の入社も増え、BELLグループ内で女性がキャリアを描いていく組織環境について考えることの重要性を感じます。
まずはそれぞれのキャリアパスについて、順番にシェアしていきましょうか。 -
入社後は当時の取締役の業務を引き継いで営業支援部を立ち上げながら、現地での提案活動や支援を増やして受注への貢献を拡大してきました。そんな中で結婚・出産。私が社内で産休・育休取得者の第一号でしたが、社内のメンバーがとにかく温かくサポートしてくれたおかげで仕事を継続できました。ここ数年は主力商品である「IBM Power」の仮想化技術の進歩に合わせてクラウドサービスの立案・運営を行い、課長補佐・課長を計3年ほど経験し、2022年に部長に就任しました。
-
新卒で入社し、基盤構築SEとしてIBM i サーバーの導入などに関する業務を担当してきました。転機は、一時的に技術相談窓口にてお客様対応に入った際、感謝の言葉をいただいたこと。直接的なやりがいを感じ、この業務に携わりたいと考えるようになりました。
結婚を機に念願だった現チームへの配属が叶い、さらには育休を経て復帰後に管理職登用のお話をいただきました。在宅勤務環境も整っているため、育児との両立も可能だろうと課長の役職に就くことを決断しました。 -
もともと他社でSEをしていましたが、ハードな勤務形態で、家族にも心配されるほどでした。そんなときに開発現場でBELLグループ社員の方と話す機会があり、社風や勤務形態に好印象を持って転職を決意。ベル・データの新規事業だった防災プロジェクトに関わった後、その事業が会社組織へと発展的に移行し「milab株式会社」が設立され、創業メンバーとして活動しています。
-
BELLグループ東京本社の人事部で勤務していましたが、配偶者の転勤に伴い関西への転居が必要となりました。上司に相談したところ、同じ人事部門のまま関西支店への異動という配慮をいただきました。この会社の柔軟な対応に感謝し、「BELLグループへどう貢献できるか」を改めて考える転機となりました。現在は部長に昇格し、本社メンバーとリモートで連携をとりながら業務に取り組んでいます。
-
入社当時は一般職のバックオフィスでした。しかし、部門が拡大するタイミングで効率的な管理体制の構築を考え、更新センターの立ち上げを主導したことをきっかけに西日本セールスサポートセンターの課長に就任し、さらに同組織が全社横断的な業務推進部に発展、部長職も兼任しています。
皆さん順調にキャリアを歩まれていますが、管理職登用の裏で葛藤や悩みなどはありましたか?
-
「上を目指そう」という志向はなかったですが、やるべきことを一つずつ対応してきた結果、次のやるべきことがこの役割だったのかな、と思っています。昇進が嬉しいというよりも、頂いたポジションでさらに自分の力を発揮しなければ、という気持ちでした。担当しているのが会社の主軸製品ということもあり、取引先との商談や社外発信の際には肩書きが説得力を高めてくれる部分もありますね。
-
私の場合は部下をリモートマネジメントする必要があることなども含めて多少躊躇しましたが、会社に望まれているのなら挑戦しようと思いました。
-
milabは設立間もないこともあり、少人数でフラットな組織。だからマネジメントに対して、そこまで肩肘張るようなことはなかったですね。
-
育児休暇後に課長職のお話をいただいたので驚きましたが、周囲からは「M.Y.さんになら任せられる」「期待している」という言葉をもらって、前向きになったことを覚えています。
-
キャリアアップを意識したことはなく、「与えられた業務の幅の中でベストを尽くそう」という意識でした。人前で話すことや自分をアピールすることも得意ではありませんでした。ただ、業務体制の構築を通して自発的に考えながら解決策を模索する方向へと思考がシフトしたように感じます。


管理職として見えた、新たな景色
-
管理職2年目でまだプレイヤー気分が抜けず、試行錯誤しているのが正直なところです。つい“自分が動くこと”を前提として仕事をしてしまいがちで。
-
まさに同じ課題感を持っています。方向性を示したり、課題に直面した際にはチーム全体が前向きな姿勢を維持できるよう声掛けをしたり、自然と周りを巻き込むような関わり方にするように工夫しているのですが。
-
私も一人で遂行しないようブレーキをかけながらですね。組織的に取り組む方が結果的に良い方向に進展し、個人の力量を超えた成果を達成できることは間違いないので。“管理職のやりがい=部下やチームの成長”という言葉をよく聞きますが、その真意が理解できるようになってきました。
-
私はチームメンバーと遠隔でコミュニケーションを取るので、タイムラグが生じていないか不安になることも。ただ、メンバー間の相互支援を促進したいという考えから、あえて詳細な指示や回答を控える場合もあります。メンバーの成長という観点では、私が遠隔地にいることがむしろ好影響をもたらしているかもしれません。
-
管理職としての醍醐味やモチベーションに関してはどうですか?
-
裁量権の広さは魅力のひとつです。上長の承認を得たうえで、各拠点への出張や宿泊も可能なため、希望通りに行動できているので業務への満足感が高いです。
-
管理職の方が業務時間をコントロールしやすいことと、経営陣との距離が近く、情報を多く得られることで今後の業務の見通しが付きやすいと感じます。
-
私自身は「管理職の本質とは何か」については常に思索して、同じく管理職のメンバーとその議題で自問自答することもあります。
-
「管理職の本質とは何か」は深いテーマですよね。
-
管理職は、メンバーが働きやすいよう環境整備や業務の円滑な進捗をサポートすることが大事で、「職位」というか「役割」だと思っていて。私は「職位」にこだわりはないけど、「役割」に対してはブラッシュアップしていきたい。ここにいる5人とも、希望して今の職位になっているわけではなく、目の前の仕事に対して成果を上げてきた結果で、それこそが真のキャリア形成の姿だと感じています。
-
確かに。管理職=上位職、というよりも、役割の変容という表現の方が適切かもしれないですね。若手の社員が魅力を感じるキャリアパスを示すことも重要だと思います。

"女性管理職"という枠を超えて。真のリーダーシップを体現
-
“従来型の管理職像”の話の流れで言及すると、リーダーシップ像を再定義する段階にきているとも考えます。
私自身社歴は長いですが、同期の男性社員が次々と昇進していく中で女性の自分に役職が付与されることなく、少なからず疑問を感じることはありました。ただ、目の前のことを達成していく充実感はあったから、そこに不満を抱くわけではなかったけど。 -
同期はどなたになりますか?
-
ベル・データの上野社長(笑)。
-
それはすごい(笑)。一つ言えるのは、私たちの入社当時からは、キャリア形成に対する組織的支援や評価体系もずいぶん整備されたように思います。
-
そういった潮流のおかげで女性管理職も増え、様々な体制が整ってきています。一方で「子育て中の今は時短勤務だから職務拡大は難しい」という声もありますし、実際に産休・育休期間がキャリア形成に影響する可能性は否定できないと思います。ただ、今はそのライフステージにいるだけで、管理職への意欲が欠如しているわけではない方もいます。例えばフレックスタイム制なども含めて柔軟な勤務形態を選択できるなど、さらなる環境整備も欠かせないと思います。それは男女問わず言えることですが。
-
本当にその通り。男女ともに実力に応じた評価体系があり、等しく個人のキャリア選択の尊重がされる環境が理想です。
社会や業界が「女性管理職を増やそう!」「女性管理職向けセミナーを開催しよう!」などと女性活躍を主導する動きに対しては逆に違和感を覚えます。性差を認識すべき場面は確かに存在しますが、女性だけがワークライフバランスを考える時代というのはもはや過去のもので、過度に準備されることは何か違う。 -
その意味では、男性だから、女性だから、管理職だから、という区分ではなく、個人が充実感を持って業務に従事できる視点は欠かせないと改めて考えますね。
夫婦間で、女性側が家庭での役割を全面的に担わなければいけないというのが潜在的にあるとするならば、会社の制度だけでは対応しようがない現実もありますが。 -
BELLグループには以前から社員の志向や意欲に応えてくれる風土があったと感じています。
私自身が希望していたチームへの異動が実現したことや、E.M.さんが所属部署の変更なく関西で業務継続されていることがその好例ですし、私の夫もBELLグループ勤務ですが、SEから営業職への転換が叶っています。そうした組織としての柔軟性は、多くの社員が長期的に就業している実績にも繋がっているように思います。 -
実際、一度退職されても再びBELLグループに復帰される方も少なくないからね。働きやすい職場文化が醸成されていることは、当社グループの強みだと実感します。
加えて、女性管理職が増えたのはここ数年かもしれませんが、それは必ずしも社会の動きに習えという動きではなく、個人の能力や成果を評価してくれる会社の体制が整ってきた結果だとポジティブに捉えています。


5人のリーダーが思い描く 自己のキャリアと組織の未来
-
BELLグループ内でスタートアップ的に立ち上がったmilabは、現在2年目を迎えています。「災害時に誰一人として取り残されない社会を創る」──その理念のもと、日々サービスの提供に取り組んでいます。まずは、安定したサービス運営の基盤を整えること。
そのうえで、自社の価値を社会に伝え、着実に実績を積み重ねていきたいと考えています。
こうした経験を通じて、エンジニア時代とは異なる視点でキャリアの幅を広げられたらと思います。 -
私のチームも人材育成を含めた体制構築に注力している段階。中長期的キャリア設計よりも、当面の業務課題解決と体制整備が優先事項ですね。よりお客様に寄り添えるチームを構築するための方策を言語化、体系化、ルール化して実務に落とし込みながら、お客様から信頼されるチーム形成を目指しています。
-
BELLグループで実現したいことは、自社のみならず他社との連携強化をさらに図りながら、IBM i から始まる次の展開を創出すること。
自分に関しては、できるだけ長く働くことかな。 -
M.M.さんのキャリアであれば、より全社的な視点での活躍も期待したいと思ってしまいますね。
-
多少は考えますが、例えば経営となると専門的知見を持つ人材の参画も含め、より包括的な視座も必要だというのが私の見解です。BELLグループに若い世代が入ってきてさらに組織を成長させて欲しいですし、私もその中で貢献度を高めながら仕事を続けたいです。
-
私自身は、担当部門において雑多になっている業務をルール化して、コスト部門から利益を生みだせる部門へと変革したいという意向があります。実務経験から培った知識を生かして、業務部門の新しい方向性を示していけるような存在になりたいですね。機能分担の観点から新たな組織編成も検討に値すると考え、さらに新たなチャレンジをしていきたいです。
-
A.Y.さんは課長兼部長として多忙ですが、補佐役となる人材の育成や採用などを検討することはありますか?
-
最近その必要性を痛感しています。一人で船に乗るよりも、一緒に船を漕いでくれる人を増やして組織力を高めた方がもっと先に行くことができますから。
-
人事としても人財の強化について重点的に取り組んでいきたいと考えています。BELLグループの今と未来について語れる仲間を増やしていきたいですね。人事業務を通して、労働力人口減少の対策などの社会課題の解決に携わっていきたいですし、会社としても「社会課題のプラットフォーマといえばBELLグループ」として世の中に認知されるよう貢献していきたいと思います。




